「働きやすい職場で働きたい」というのは多くの人が思うことで、事業所はそのための努力を惜しまないようにしましょう。この努力を怠ると、最悪の場合には事業所の存続にかかわる事態になりかねません。
そうならないためにも「労働衛生」の考え方をしっかりと理解することが大切です。労働衛生は労働安全衛生法によって規定されており、さまざまな取り決めが義務化されています。これを守らないことはコンプライアンス違反となり、罰金が科されてしまうこともあるため注意が必要です。
この記事では、労働衛生の基本的な考え方から、その具体的な対策までを丁寧に解説していきます。自社の状況と照らし合わせながら、従業員が働きやすい職場づくりに役立ててもらえれば幸いです。
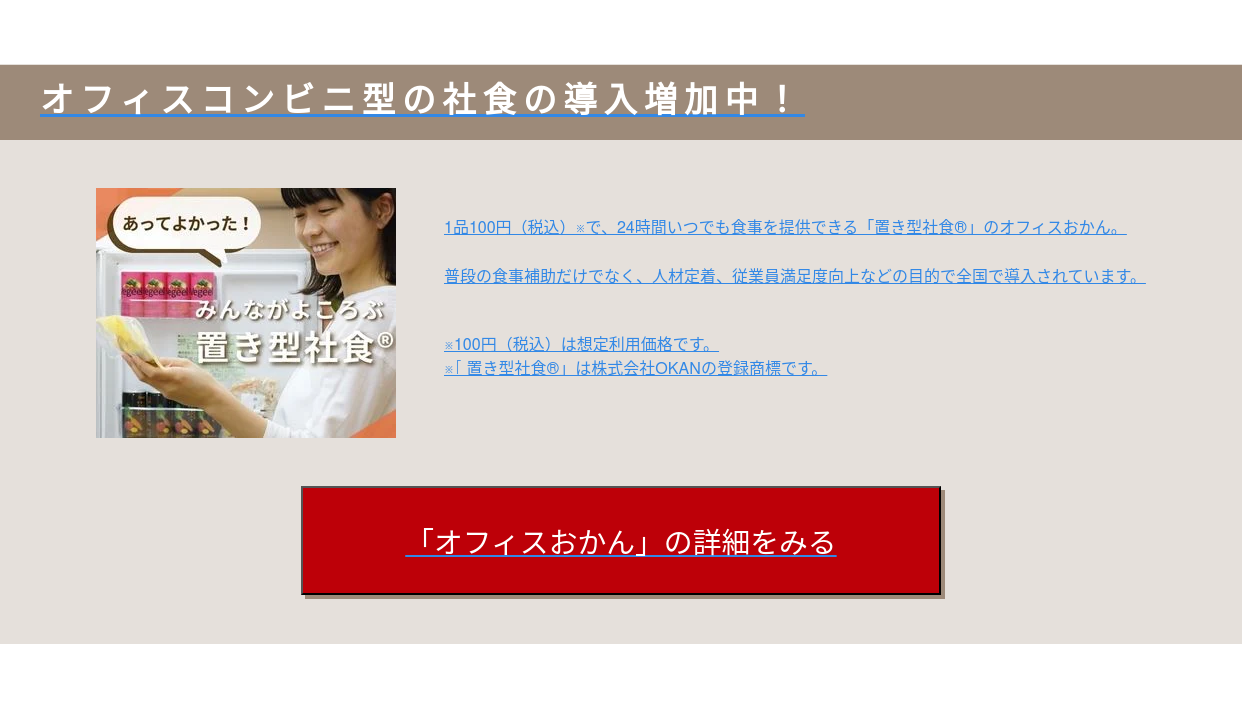
労働衛生とは?
「労働衛生」とは、労働者の健康状態を維持するために職場の環境や条件を改善することであり、産業衛生や工場衛生と呼ばれることもあります。この労働衛生は「労働安全衛生法」で規定されているため、事業所は労働者の健康維持・増進のための環境整備に努めなくてはいけません。
労働衛生に関する規定は、1947年に制定された労働基準法の中に盛り込まれていました。しかし、高度経済成長期に入り大規模工事や生産拡大が進むと、労働災害の被害者が発生した事実を受けて1972年に労働者を守る目的で現在の労働安全衛生法が成立しました。
出典:「労働安全衛生法の施行について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1&pageNo=1)(2024年4月15日に利用)
労働衛生の3管理とは?
「労働衛生の3管理」とは、作業環境管理・作業管理・健康管理のことです。労働衛生管理の基本となる考え方として、労働衛生管理体制の確立と労働衛生教育の2つを含め、5管理とすることもあります。ここでは3管理がそれぞれ「何を意味しているのか」を詳しく確認していきましょう。
出典:「労働衛生の3管理[安全衛生キーワード] 」(厚生労働省)(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html)(2024年4月15日に利用)
出典:「基本的な労働衛生対策と労働安全衛生マネジメントシステムについて 」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000490657.pdf)(2024年4月15日に利用)
作業環境管理
「作業環境管理」とは、作業を行う環境における有害因子(作業の妨げとなる要因)を把握し、現場作業者にとって適切な作業環境へと改善および管理することを意味しますなお、ここでいう作業環境における有害因子とは、危険物や粉じん、不適切な温度、騒音などを指します。
出典:「労働衛生の3管理[安全衛生キーワード]」(厚生労働省)(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html)(2024年4月15日に利用)
作業管理
「作業管理」とは、従業員の健康を考えたうえで、携わる作業を適切に管理することです。作業環境管理との違いは、作業管理が作業内容を対象にしているのに対して、作業環境管理は作業を行う場所および空間を管理の対象としてます。
出典:「 Q17.労働衛生対策を進めるにあたり、労働衛生管理体制を確立するとともに、労働衛生教育を徹底し、労働衛生3管理を総合的に実施することが必要ときいていますが、労働衛生3管理とはなんですか?」(東京都労働局)(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q19.html)(2024年4月15日に利用 ※このページは記事作成時点では参照可能でしたが、現在は閉鎖されています。)
健康管理
「健康管理」とは、従業員の健康状態を健康診断や保健指導などでチェックすることです。このような取り組みを継続することで、健康面での早期の発見がしやすくなり、改善に向けた助言がしやすくなるでしょう。
なお、近年では従業員の高齢化に伴う健康保持や、労働適応能力を維持できるような対策も求められています。また、最近では身体的な健康に加え、心理的安全を踏まえたメンタルヘルスのケアにも注目が集まっています。全ての従業員が心身ともに健全な状態で生産性を上げて仕事ができるよう、事業所側がサポートをしていく必要があると言えるでしょう。
出典:「労働衛生の3管理[安全衛生キーワード]」(厚生労働省)(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html)(2024年4月15日に利用)
労働衛生を推進する理由
労働衛生対策を行うことのメリットを紹介していきます。労働衛生に取り組む利点と併せて、対策を怠る場合のリスクも理解しておきましょう。
事故を未然に防ぐ
安全労働衛生法が成立した背景の一つとして、労働災害のリスクが挙げられます。労働衛生対策を講じて、作業時の事故を防止することは事業所において大変重要です。過去には、長時間労働を理由に精神的に苦しめられ、命を絶つ事態が社会問題として注目されました。こういったものも、労働災害の一つとして含まれます。
このように、労働中の「事故」というのは車や機械が絡む物理的な事故だけではありません。精神面が起因となるトラブルにも気を配る必要があると言えるでしょう。
人材の流出を防ぐ
職場の労働環境が劣悪な場合、離職者が増えるのは不思議ではありません。今は、SNSや求人サイトの口コミ情報などですぐに職場環境に関する噂が広まり、求人広告を出してもエントリー数が少ない、人が集まらないという事態が発生することも考えられます。
事業所側としても持続可能な経営につなげるためには、従業員が働きやすいと思える職場環境づくりを考えることが必要と言えるのです。
企業のブランド価値低下を防ぐ
前述した通り、会社の評判は瞬く間に広まります。しかも、ネガティブな噂であればあるほど、拡散するスピードは速くなる傾向にあり、企業としてのブランド価値低下につながってしまうでしょう。
「過労死・長時間労働・ブラック企業」などのイメージが、一度定着してしまうと、それをクリーンなイメージにするためには長い時間がかかります。事業所側としても、社外に良い印象を与え、信頼を得るためにも、労働衛生の対策に注力することが重要と言えるでしょう。
従業員のやる気低下を防ぐ
職場環境が悪ければ、従業員は働きづらく感じ、モチベーションの低下につながります。働きがいや生産性の向上につなげられるよう、労働衛生対策を入念に考える体制を整えましょう。
労働安全衛生強化のためにするべきこと
ここでは、労働安全衛生を強化するためにするべきことについて詳しく説明をしていきましょう。
安全衛生管理体制の構築
労働安全衛生法では、事業所規模や業種に応じて総括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者、産業医の選定、いわゆる安全衛生管理体制の整備が義務付けられています。たとえば、201~500人の従業員がいる職場では、衛生管理者2人を設定します。
出典:「衛生管理者について教えて下さい。」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html)(2024年5月9日に利用)
またその他の決まりとしては、常勤50人以上の事業所では月に1度以上安全衛生委員会を開くという規定なども設けられています。
出典:「安全衛生委員会を設置しましょう」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0902-2a.pdf)(2024年4月15日に利用)
労働衛生の3管理についての具体策
次に、労働衛生の3管理についての具体的な対策を見ていきましょう。
作業環境管理
作業環境管理とは、作業場の明るさや温度、湿度、気流、臭い、騒音、作業者の動線、人員の密度、危険作業の有無などが管理の範疇です。労働衛生管理のなかでは優先的に考えたい管理であり、継続的に職場環境をチェックし、働きやすさ改善を進めましょう。
特に粉じんや放射線などといった人体にリスクを伴うことに関しては、作業環境の安全性を確認することが必要であり、作業環境測定を実施しなくてはなりません。
作業管理
作業管理についての具体策も見ていきましょう。
- 作業をマニュアル化する
作業をマニュアル化することで人的ミスを防ぐことができ、労働災害リスクを抑えることが可能です。マニュアル化をするということは、一つひとつ作業を見直すきっかけにもなり、リスクの洗い出しにも有効です。
- 正しい姿勢で作業ができるよう改善する
工場やテレアポのように、長時間にわたって同じ姿勢で仕事をする職場では、従業員が正しい姿勢で作業をこなせるような環境を整備しましょう。無理な姿勢が続くと、腰痛や膝痛などにつながる危険性があるので、机と椅子の高さを調節したり、立ち仕事の合間に座れるようにしたりするなどといった作業環境の改善にも心を配る必要があります。
- 作業時間を適正化する
長時間労働が続くと、従業員の集中が続かなくなりがちです。特に危険を伴う作業を行う場合、ケガや事故につながりかねません。定期的に休憩を取る、作業員を増やし一人当たりの労働時間を減らすなどの対策が必要です。いかに従業員の負担を減らす仕組みがつくれるかがカギとなるでしょう。
健康管理
健康管理では、従業員の疲れやストレスをいかにケアできるかがポイントとなります。身体的なケアだけでなく、精神的な状態にも着目した対策が必要です。
- 相談できる窓口を設置する
従業員が心身ともに安定した状態で仕事ができるよう、相談窓口を常設します。「事業所内の窓口には相談しづらい」と感じる従業員もいる可能性もあるため、外部委託として相談しやすい環境を設けておきましょう。
- 休憩室やシャワー室を確保する
野外での作業や、汗をかいたり、体が汚れたりするような作業を行う事業所では、休憩室やシャワーを設置します。これらの施設を清潔に保ち、従業員が快適に利用できるようにすることも忘れてはいけません。
労働衛生対策の助成金
労働衛生対策の助成金として産業保健関係助成金(ストレスチェック助成金、職場環境改善計画助成金、小規模事業場産業医活動助成金など)として運用されてきましたが、2022年から「団体経由産業保健活動推進助成金」として労働者の心身の健康管理を行っています。
こちらの助成金は、中小企業を支援する組織団体などが、傘下にある中小企業などに対し、産業医といった医療従事者や産業保健サービスを提供する事業者と契約することで、従業員に産業保健サービスを提供した際に費用の一部を助成するものです。
【条件】※2023年10月以降
- 助成対象:産業保健サービス+事務費用
- 助成率:90%
- 助成上限額:500万円、一程の要件を満たした場合は1,000万円
- 助成回数:1団体につき年度で1回のみ
【対象となる産業保健サービス】
- 保健指導
- 健康診断結果の意見聴取
- 面接指導、意見聴取
- 健康相談対応(※)
- 治療と仕事の両立支援
- 職場環境の改善支援(※)
- 健康教育研修、事業者と管理者向けの産業保健に関する周知啓発(※)
(※化学物質の取り扱いに関連した健康相談、改善指導、研修などを含む)
出典:「団体経由産業保健活動推進助成金の開始について」(厚生労働省ホームページ)(https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_01538.html)(2024年4月16日に利用)
出典:「団体経由産業保健活動推進助成金のご案内」(厚生労働省ホームページ)(https://www.mhlw.go.jp/content/001151913.pdf)(2024年4月16日に利用)
まとめ
従業員が働きやすい環境を整備することは、事業所の義務であり責任でもあります。利益追求が過ぎると、どうしても労働衛生の取り組みがおろそかになりがちなので、持続可能な経営と人材活用につなげるためにも労働衛生に取り組まなければなりません。
事業所側としては、職場の環境チェックを定期的に行ったり、従業員アンケートを実施したりして、労働環境で改善すべきところは改善し、従業員が働きやすいと思える環境づくりに努めていきましょう。

